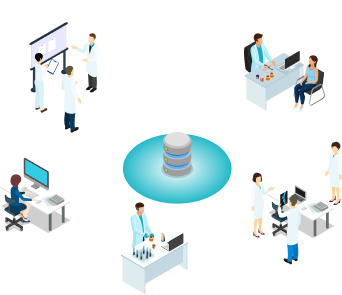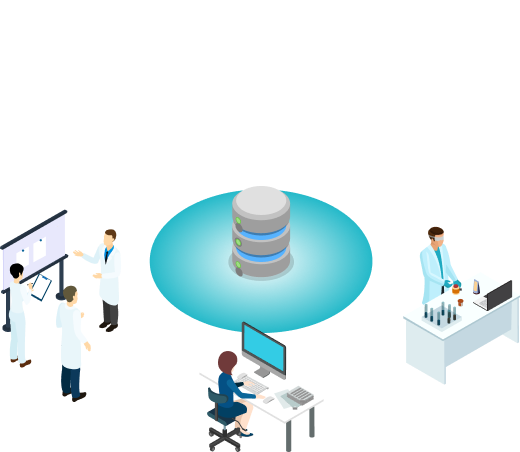ステミラック注
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):4900401X1026
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 先発品(後発品なし)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞
- 英名(商品名)
- -
- 規格
- 1回分
- 薬価
- 15,234,750.00
- メーカー名
- ニプロ
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2025年9月改訂(第1版)
- 告示日
- 2019年2月25日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- 2019年3月版
- 医薬品マスタ削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
-
禁止物質あり(使用の適否を判断するものではありません)
競技会区分:常に禁止(競技会検査及び競技会外検査)
セクション:S5. 利尿剤及び隠蔽剤
競技会区分:常に禁止(競技会検査及び競技会外検査)
セクション:M1. 血液及び血液成分の操作
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
脊髄損傷に伴う神経症候及び機能障害の改善(ただし、外傷性脊髄損傷で、ASIA機能障害尺度がA、B又はCの患者に限る)。
用法用量
骨髄液の採取は、患者の全身状態等を考慮した上で、脊髄損傷受傷後31日以内を目安に実施する。また、製品が製造され次第、可能な限り速やかに投与する。
6.1. 本品の原料採取時に行う事項
6.1.1. 患者から末梢血を採取する。採取した末梢血は採血キットの構成体である容器(ニプロセルトリー血清用)に入れ密封する。末梢血の入った容器は製造販売業者の指定する施設へ運搬する。
6.1.2. 患者から骨髄液を採取する。採取した骨髄液は、骨髄採取キットの構成体である骨髄希釈液DMEMとともに容器(ニプロセルトリー骨髄用)に入れ、混合して密封する。骨髄液の入った容器は製造販売業者の指定する施設へ運搬する。
6.2. 本品を患者に適用する際に行う事項
自己骨髄間葉系幹細胞として1回0.5×10の8乗個~2.0×10の8乗個(最大投与量は体重1kgあたり3.34×10の6乗個)を、生理食塩液で3倍以上に希釈しながら、本品の流量0.7~1.0mL/分を目安に点滴静注する。
(用法及び用量又は使用方法に関連する注意)
7.1. 本品の原料採取時に行う事項に関する注意
7.1.1. 次記の標準的な採取スケジュール及び標準採取量を参考に、末梢血及び骨髄液採取に伴うリスクを勘案し、患者の年齢、体重、及び全身状態等を踏まえた適切な採取計画の策定を行った上で本品を使用すること。
1). 受傷から本品適用の決定まで:約2週間。
2). 末梢血採取1回目、末梢血採取2回目:実施時期の目安は受傷約2週間後~4週間後、2回目までの採取量の目安:約480mL。
3). 骨髄液採取:実施時期の目安は受傷後31日以内を目安に実施、採取量の目安は標準採取量:50mL、最小採取量:20mL。
4). 末梢血採取3回目、末梢血採取4回目:実施時期の目安は受傷約4週間後~6週間後、1回目から4回目までの総採取量の目安:約960mL。
7.1.2. 末梢血又は骨髄液の採取については、末梢血又は骨髄液の採取に関する十分な経験を持つ医師により採取を行うこと。
7.1.3. 末梢血又は骨髄液の採取は、清潔な環境下で行うこと。
7.1.4. 抗凝固剤による治療中や抗血小板剤による治療中の患者から骨髄液を採取する際には、必要に応じて一時治療を休止し、患者の容態に留意すること。
7.1.5. 小児から骨髄液を採取する場合、腸骨稜の厚さが成人に比べて薄く、腸骨を貫通するリスクがあるため、慎重に作業を実施すること。
7.1.6. 末梢血又は骨髄液の採取、運搬は、製造販売業者の指定する専用の容器で行うこと。
7.1.7. 末梢血又は骨髄液を入れた容器はキャップを上側にして保管すること。
7.1.8. 末梢血又は骨髄液の採取後は、十分な止血を行い、血腫や感染等に注意すること。
7.1.9. 骨髄穿刺が原因の疼痛が発生した場合は、適切な処置を行うこと。
7.2. 本品を患者に適用する際に行う事項に関する注意
7.2.1. 本品の最大投与量は体重1kgあたり3.34×10の6乗個であるため、患者の体重によっては製品全量を投与しない場合があることに留意し、投与前に必ず最大投与量の確認を行い、必要に応じて投与量の調整を行うこと。
7.2.2. 細胞を静脈内投与することに起因するリスクとして、塞栓症、血栓形成及び血管内溶血が発生する可能性があるため、本品の流量が最大1.0mL/分を超えないように投与すること〔8.4参照〕。
改訂情報
-
類似した薬効の薬
よく一緒に見られている薬
医師の処方により使用する医薬品。



 で医薬品を比較する
で医薬品を比較する