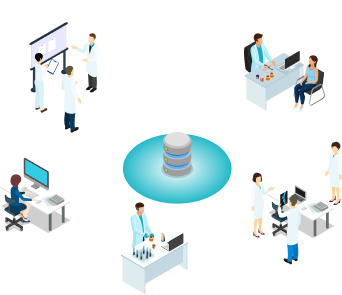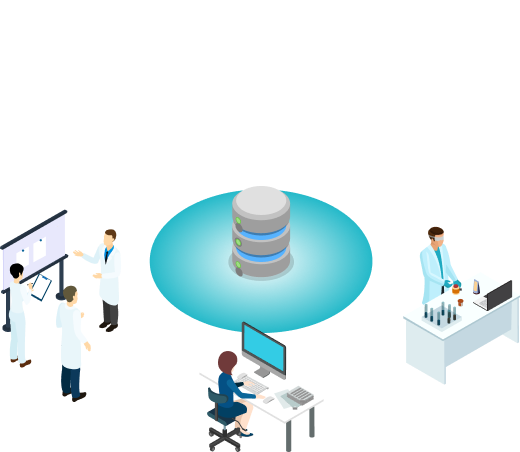ステラーラ皮下注45mgシリンジ
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):3999431G1025
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 先発品(後発品あり)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- ウステキヌマブ(遺伝子組換え)キット
- 英名(商品名)
- Stelara
- 規格
- 45mg0.5mL1筒
- 薬価
- 198,887.00
- メーカー名
- ヤンセンファーマ
- 規制区分
- 劇薬
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 免疫抑制薬〔ヒト型抗ヒトインターロイキン−12/23p40(IL−12/23p40)モノクローナル抗体〕
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2025年6月改訂(第5版)
- 告示日
- 2011年3月11日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- -
- 医薬品マスタ削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). 既存治療で効果不十分な次記疾患:尋常性乾癬、乾癬性関節炎。
2). 中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)。
3). 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈尋常性乾癬及び乾癬性関節炎〉次のいずれかを満たす尋常性乾癬又は乾癬性関節炎患者に投与すること[1)紫外線療法を含む既存の全身療法(生物製剤を除く)で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積の10%以上に及ぶ患者、2)難治性の皮疹又は関節症状を有する患者]〔1.4参照〕。
5.2. 〈クローン病〉過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、アザチオプリン等)等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること〔1.4参照〕。
5.3. 〈潰瘍性大腸炎〉過去の治療において、他の薬物療法(ステロイド、アザチオプリン等)等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること〔1.4参照〕。
用法用量
〈尋常性乾癬及び乾癬性関節炎〉
通常、成人にはウステキヌマブ(遺伝子組換え)として1回45mgを皮下投与する。初回投与及びその4週後に投与し、以降12週間隔で投与する。
ただし、効果不十分な場合には1回90mgを投与することができる。
〈クローン病/潰瘍性大腸炎〉
ウステキヌマブ(遺伝子組換え)の点滴静注製剤を投与8週後に、通常、成人にはウステキヌマブ(遺伝子組換え)として90mgを皮下投与し、以降は12週間隔で90mgを皮下投与する。なお、効果が減弱した場合には、投与間隔を8週間に短縮できる。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈効能共通〉本剤と他の生物製剤の併用について安全性及び有効性は確立していないので併用を避けること。
7.2. 〈尋常性乾癬及び乾癬性関節炎〉本剤による治療反応が得られない場合、投与開始から28週以内には増量を含めて治療計画を再考すること。また、尋常性乾癬及び乾癬性関節炎の場合、増量を行っても十分な治療反応が得られない場合、本剤の投与継続を慎重に再考すること。
7.3. 〈クローン病/潰瘍性大腸炎〉ウステキヌマブ(遺伝子組換え)点滴静注製剤による導入療法の初回投与8週後に、本剤の皮下投与を開始すること(導入療法における用法・用量は、ウステキヌマブ(遺伝子組換え)の点滴静注製剤の電子添文を参照すること)。
7.4. 〈クローン病/潰瘍性大腸炎〉本剤の8週間隔への投与間隔短縮は、本剤の皮下投与中に効果が減弱した患者に対し、本剤の皮下投与開始から8週以降に行うことができる。クローン病/潰瘍性大腸炎の場合、本剤の投与間隔を短縮しても16週以内に治療効果が得られない場合、投与を継続しても効果が得られない可能性があることから、本剤の投与継続の必要性を検討すること。
7.5. 〈クローン病/潰瘍性大腸炎〉本剤の皮下投与開始後、本剤の2回目の皮下投与までに治療反応がない場合、投与を継続しても効果が得られない可能性があることから、本剤の投与継続の必要性を検討すること。
改訂情報
2025年7月8日 DSU No.337 【その他】
【15.1臨床使用に基づく情報】(一部改訂)
海外の尋常性乾癬、乾癬性関節炎、クローン病、潰瘍性大腸炎を対象とした臨床試験(第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験)において、プラセボ対照期間の非黒色腫皮膚癌を除く悪性腫瘍の発現頻度は、本剤投与群が0.11/100人年(1例/929人年)、プラセボ投与群が0.23/100人年(1例/434人年)であった。非黒色腫皮膚癌の発現頻度は、本剤投与群が0.43/100人年(4例/929人年)、プラセボ投与群が0.46/100人年(2例/433人年)であった。また、対照及び非対照期間において、6710名(15205人年)に本剤が投与された。その追跡調査中央値は1.2年で、尋常性乾癬を対象とした臨床試験では3.2年、乾癬性関節炎を対象とした臨床試験では1.5年、クローン病を対象とした臨床試験では0.6年、潰瘍性大腸炎を対象とした臨床試験では2.3年であった。非黒色腫皮膚癌を除く悪性腫瘍の発現頻度は、0.50/100人年(76例/15205人年)で、主なものは前立腺癌、黒色腫、結腸直腸癌、乳癌であった。本剤投与群で報告された悪性腫瘍の発現頻度は、一般人口で予測される発現頻度と同様であった(標準化発生比:0.94[95%信頼区間:0.73、1.18]年齢、性別、人種により補正)。非黒色腫皮膚癌の発現頻度は0.46/100人年(56例/11545人年)であった。皮膚基底細胞癌と皮膚有棘細胞癌の発現比率は3:1であり一般人口で予測される発現頻度と同様であった。
よく一緒に見られている薬
医師の処方により使用する医薬品。



 で医薬品を比較する
で医薬品を比較する