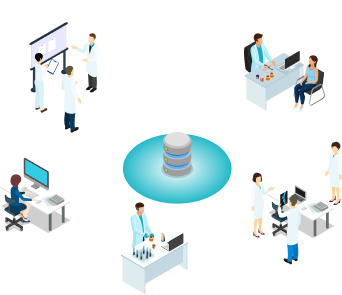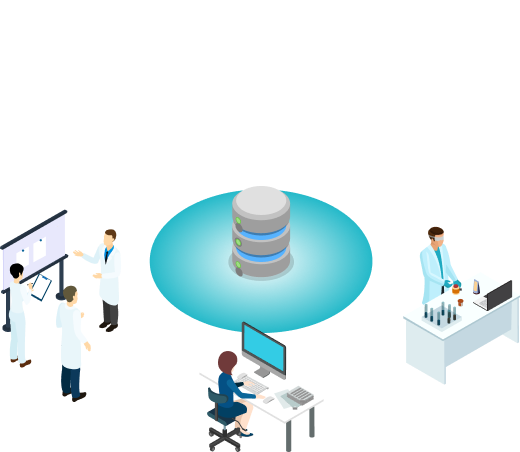近年、情報通信機器の普及に伴い医療の分野でも「オンライン診療」が活用される場面が増えています。自宅等から医師の診察を受けられる便利な仕組みですが、利用にあたってはいくつかの注意点も存在します。本記事では、オンライン診療の概要について説明します。
オンライン診療の定義と背景
オンライン診療とは、スマートフォンやパソコン等の情報通信機器を用いて、医師と患者がリアルタイムに映像と音声のやり取りをしながら行う診療行為を指します。これは厚生労働省の定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って実施される、公的な医療行為とされています。
この制度が普及した背景には、情報通信技術の進展に加え、新型コロナウイルス感染症への対応、へき地・離島における医療アクセスの確保といった社会的な要請があります。
オンライン診療のメリットと注意すべき点
1.オンライン診療を利用するメリット
オンライン診療では以下のメリットがあります。
・通院負担の軽減:医療機関への移動時間や交通費がかからず、身体的な負担も軽減されます。
・院内感染リスクの低減:他の患者と接触する機会がないため、感染症の拡大防止につながります。
・医療へのアクセス向上:へき地や離島に在住している方や、身体的な理由で通院が困難な方でも、医療を受けやすくなります。
2.オンライン診療を利用する際に注意すべき点
多くのメリットがある一方で、オンライン診療の利用にあたっては以下の注意点があります。
・対象疾患の制限:オンライン診療では画面越しの視診や問診が中心となり、触診や聴診、各種検査といった物理的な診察行為は行えません。このため、全ての疾患や症状がオンライン診療の対象となるわけではなく、対面診療が必要であると医師が判断することがあります。
・処方薬の制限:初診のオンライン診療では、安全性等の観点から処方が制限されている医薬品があることや、処方日数も制限されることがあります。
・情報伝達の重要性:オンライン診療は画面越しの限られた情報で診察を行うため、対面診療に比べて医師が得られる情報が限定的です。この情報量の差を埋めるためにも、患者側から自身の症状や既往歴、服用中の薬、アレルギーの有無等を正確に伝えることが重要です。
・環境の準備:スムーズな診療のためには、安定したインターネット接続環境が不可欠です。また、会話の内容が他人に聞こえないプライバシーが確保された場所を、患者自身で準備することが求められます。
→ データインデックスが提供する医薬品データベース「Xlib」の詳細はこちら
オンライン診療と医療保険
1.オンライン診療と診療報酬制度
日本の医療制度では、診察や検査、薬の処方といった医療行為に「診療報酬」と呼ばれる公定価格が定められています。オンライン診療も、厚生労働省の指針に基づいて行われる正規の医療行為であり、この診療報酬制度の対象です。対面診療と同様に、オンライン診療で行われる診察や処方箋の発行等にも、それぞれ所定の点数が定められています。
2.自己負担割合は対面診療と同じ
オンライン診療は診療報酬制度の対象であるため、原則として医療保険が適用されます。
そのため、患者が支払う際の自己負担割合は、対面診療を受ける場合と変わりません。例えば、3割負担の患者であれば、オンライン診療にかかった診療報酬のうち、3割を自己負担額として支払うことになります。ただし、診察料とは別に、アプリの利用料や通信料といった費用が自己負担で発生する場合があります。
3.自由診療の場合
美容皮膚科の一部メニューや男性型脱毛症治療等、疾患や治療内容によっては医療保険が適用されない「自由診療」としてオンライン診療が行われる場合があります。この場合、医療機関が独自に料金を設定しており、費用は全額自己負担となります。
まとめ
オンライン診療は、時間や場所の制約を減らし、医療へのアクセスを向上させる便利な選択肢です。一方で、対面診療にしかできないことも多く存在するため、対面診療と適切に使い分けることが重要です。
また、対象疾患や処方薬の制限等があるため、遵守すべき事項を理解し、適切に実施することが求められます。
―参考資料―
厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233212.pdf)
厚生労働省 オンライン診療の利用手順の手引書(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001237765.pdf)